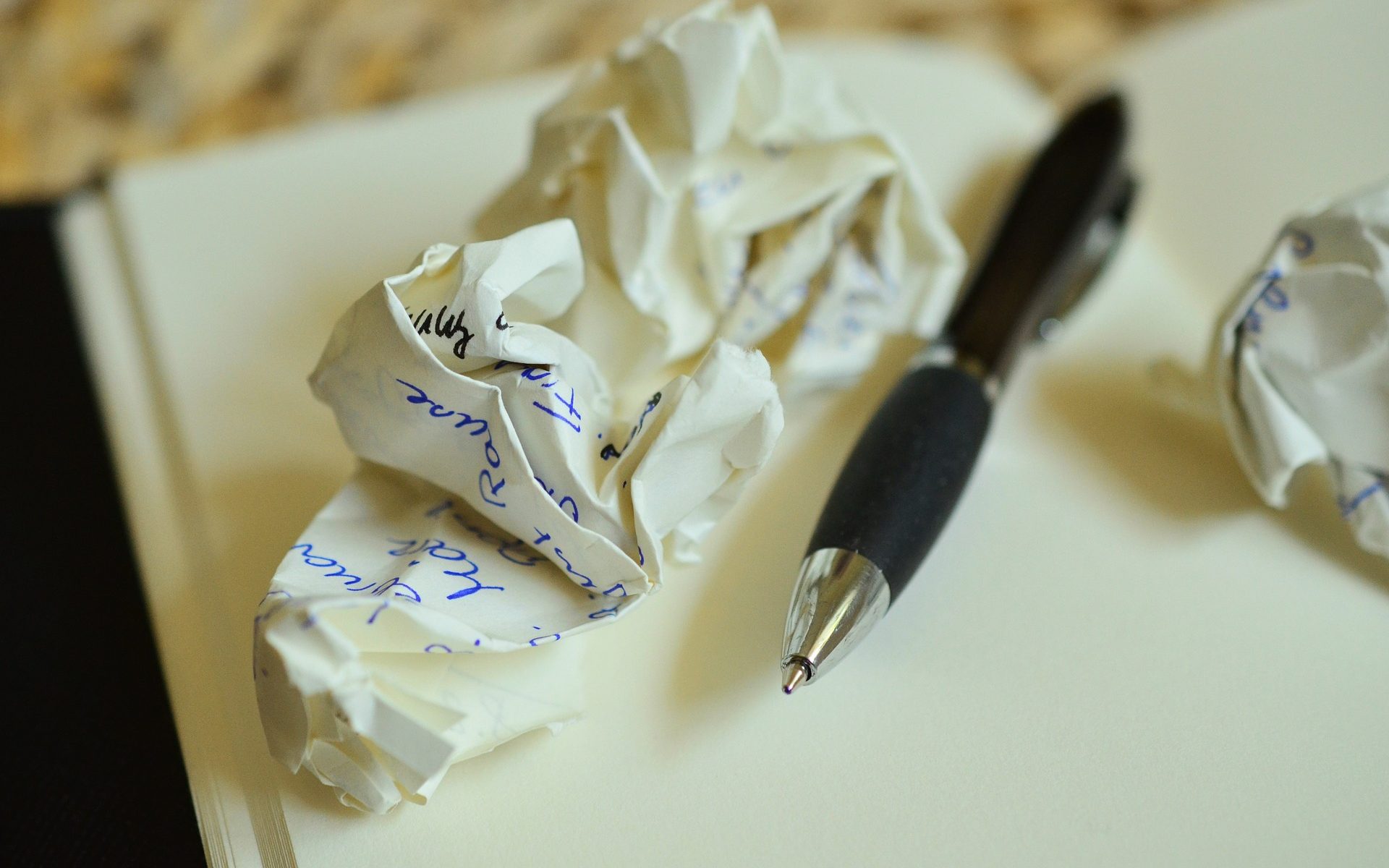最近は地価も上がってきており、平成30年5月、私の住む京都市ではインバウンドの増加もあってか、地価が上昇し、固定資産税・都市計画税は昨年比で8%程度上昇したようです。世の大家さんとしては賃上げをしたいと考えている方も多いのではないかと思います。そこで、今回は、競売事件ではなく、普通の賃貸借契約の中で賃上げの請求が来たときの対処法を考えていきたいと思います。
そもそも賃貸契約の途中で値上げなんて出来るの?

ご自宅の賃貸借契約のほとんどの普通賃貸借契約(定期賃貸借契約でないもの)は、契約期間を1年とか2年にしているのではないかと思います。しかし、契約期間中だからといって、契約の変更が出来ないと記載している契約書は少ないのではないでしょうか。
例えば退去の連絡。これは法的には契約の解除に関する通知になるのですが、一般的な普通賃貸借契約では、借主は1ヶ月前に通知すれば退去できる、となっているのではないでしょうか。すなわち契約途中でも解除することが出来ることを定めています。
家賃についても「不相応になったとき」などとしながらも、値上げが出来る規定を置いている場合が多いのではないかと思います。契約とは、貸主と借主の合意ですから、値上げが出来ない、と定めていない限り、お互いが合意すれば家賃も変更することが出来ます。
同意しなければ、値上げは出来ないの?

これについては「そうです。」の一言で済んでしまいます。先ほども書きましたが、契約はあくまでも当事者同士の合意によってのみ成立します。いくら大家さんが「絶対値上げをする」と言っても、借主であるあなたが合意しなければ値上げすることは出来ません。ただし、もとの家賃があまりに安い場合などは、裁判によって、妥当な賃料を定めて貰うことが出来ます。裁判によって合意を強制されるのです。
家賃の値上げで裁判!?

大家さんにとっても大切な資産であるお部屋を貸しているのですから、正当な賃料を払って貰う権利があります。旧来、大家と店子の関係は、大家さんが圧倒的に強い立場であったことから、店子(賃借人)保護の規定がたくさん定められてきました。しかし、近年改正が相次ぎ、お互いの関係はずいぶんフラットになりました。
そこで、ずいぶん昔から安い賃料でお住まいの方などに対して、大家さんの代替わり(相続や売買)などを機に、賃料を更改したいという話も聞くようになりました。このような場合、裁判に詳しい不動産業者や弁護士が協力して賃料の増額通知を行っていることが多いです。そこで値上げに応じなければ、裁判手続きに移行することになるのです。一般的には、内容証明郵便による通知→調停手続き→訴訟手続きの順に移行していき、最後には判決によって賃料が定められます。
裁判は避けられないの!?どうしたらいい?
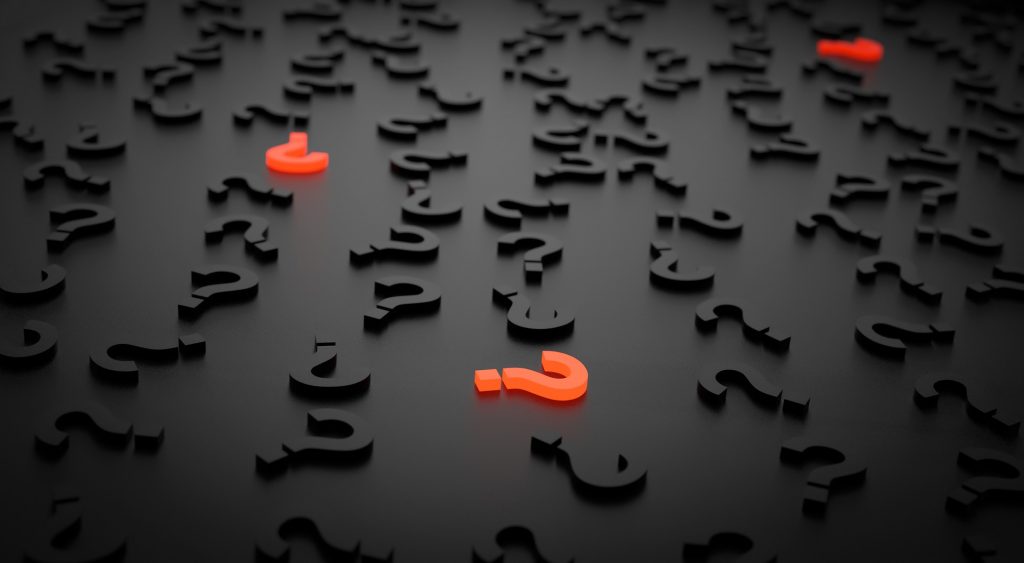
基本的に、裁判を受ける権利は誰にでもありますので、裁判をすること自体は止められませんし、闇雲に裁判を怖がる必要もありません。ただし、対応を間違えると、あなたにとって不利な内容が決まってしまうこともありますので、注意が必要です。裁判手続きに限らず、新たに不利な条件で合意してしまったり、逆に裁判所からの連絡まで放置してしまうと、取り返しがつかなくなることがあります。
取り急ぎ、賃料増額通知が来た際に行っておかなければならないことがあります。それは「賃料を払い続ける」と言うことです。
賃料を払うって、当たり前ではないのですか?

賃料くらいちゃんと払うよ、と思っている方も多いと思いますが、弁護士が関与せずに賃料増額通知が発送された場合、稀に「増額後の賃料でないと受け取りません」と通知してくることがあります。この場合、家賃を持参しても受け取ってくれなかったり、増額に応じられないからといって送金しない方もいらっしゃいます。
しかし、賃料を支払わない、という行為は「債務不履行」という状態になりますので、相手(大家さん)に有利に働きます。場合によっては、賃料不払いを理由に契約を解除され追い出されることもあります。増額後の賃料でないと受け取らない、という通知は得てして、これを狙っていることがあります。
契約を解除されないために出来ること
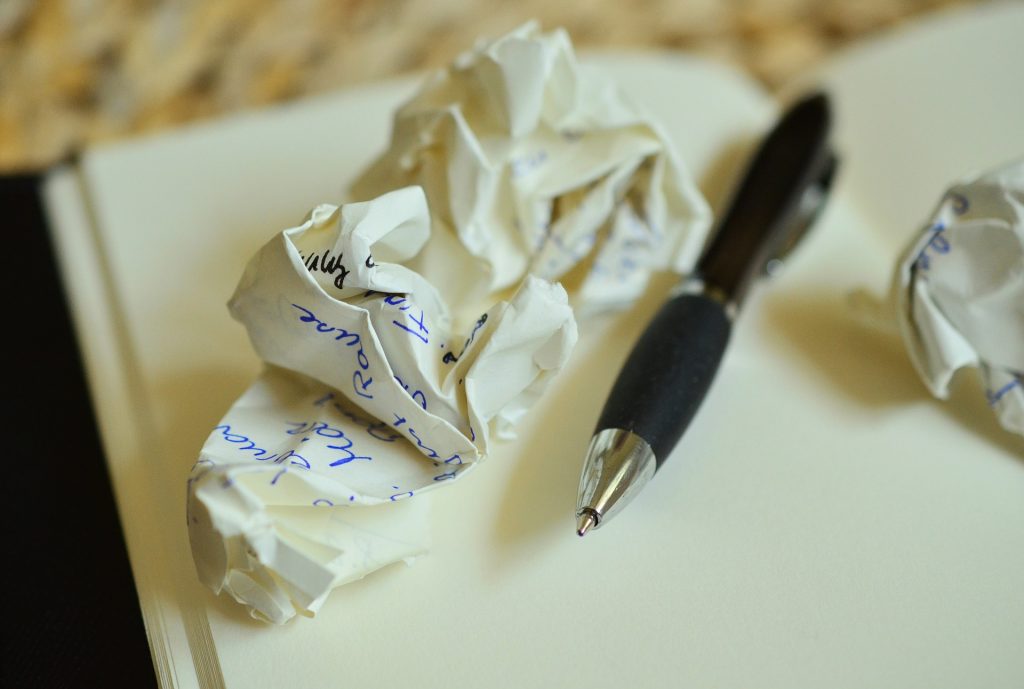
賃料増額通知が来たときに考えなければいけないことは、どうやって今までどおりの家賃を支払うか、ということです。その答えは「供託」です。お住まいの地域を管轄する法務局の本・支局で家賃を供託する手続きをする必要があるのです。現状の家賃を供託すれば、家賃は支払っていることになりますので、裁判の手続きに移行したとしても、怖がることはありません。賃料不払いを理由に契約解除、という事態は避けられます。ただし、現在の家賃があまりに安い場合は、裁判の手続き中に適正な家賃まで引き上げられてしまいますのでご注意下さい。
以上、今回は、突然家賃の値上げ通知が来たときの対処法を書いてみました。
最近は法務局も親切ですので供託のやり方は親切に教えてくれます。しかし、裁判手続きに移ったときは、ぜひ専門家(弁護士)に相談してみてください。色々アドバイスして貰えると思いますよ。